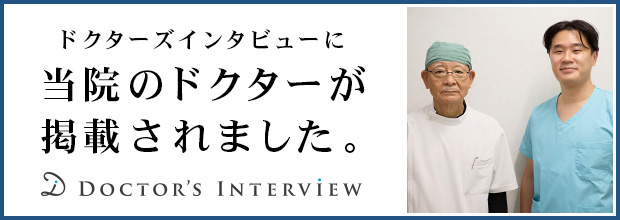鼻中隔矯正術
鼻中隔弯曲症の病態と適応
鼻中隔(びちゅうかく)とは鼻の中を左右に分けている仕切り板(軟骨、骨)のことです。正常の人でも全くの対称ではなく、左右のどちらかに曲がっていますが、曲がりがわずかであれば、鼻づまりを起こすことはありません。しかし、極端に曲がっている人は、鼻が年中つまっていることがあります。そのため、口呼吸をするようになり、咽頭部の乾燥や頭重感を自覚したり、集中力不足、注意力散漫、いびき、眠りが浅くなる(無呼吸の悪化)などの症状があらわれます。よって鼻中隔弯曲による症状で日常生活に支障をきたす場合は手術の対象となります。また、慢性副鼻腔炎があり、鼻中隔の弯曲が鼻副鼻腔の換気障害に悪影響を及ぼしている場合も副鼻腔手術に併用して鼻中隔手術を行うことがあります。
麻酔方法
当院では、局所麻酔のみで手術を行なっております。3,000倍希釈のボスミン(血管収縮薬)と4%キシロカイン(局所麻酔薬)にひたしたガーゼを鼻腔内に挿入し麻酔します。 20-30分してある程度粘膜表面の麻酔が効いてきたら、手術前に追加でエピネフリン含有キシロカインで注射麻酔をします(歯科治療で使う麻酔と同じようなものです)。
手術方法
鼻中隔は前方が軟骨、後方が骨でできており、それを粘膜が覆っている構造です。
鼻の穴から1cm程度入ったところの鼻中隔を切開し、粘膜を温存して弯曲している部位のみの軟骨と骨を取り除きます。その後切開部を1-2針縫合して概ね終了です。
アレルギー性鼻炎や肥厚性鼻炎を合併して下鼻甲介の腫大が鼻づまりの原因となっている患者さんには、同時に下鼻甲介粘膜凝固術も行うことがあります。
手術終了後、止血と創部圧迫のため、両側の鼻の中に圧迫スポンジやガーゼ等を入れます。
術前・術後の注意
- 手術予定時間の2時間前より、飲食は避けて下さい。
- 当日は、入浴・洗髪は禁です。手術の内容あるいは、合併症の状態によっては、指示あるまで入浴・洗髪の制限をします。しばらくの間は飲酒も禁止です。術後は出来るだけ安静にして下さい。家事やデスクワーク程度の労働は可能ですが、力仕事や運動は術後2週間中止して下さい。
- 持続的に出血する場合は、座って少し前かがみになり、鼻翼(小鼻のところ)を強く15分程度圧迫してください。多くは圧迫で止血します。
合併症
- 出血:術後の鼻血を予防するため、手術後鼻の中に圧迫スポンジやガーゼ等を挿入します。術後数日たって抜きますが、その後出血があった場合、再挿入が必要です。
- 感染:手術後、血の塊や圧迫スポンジ、ガーゼ等の影響で鼻の中に感染が起こることがあります。予防のため、抗生剤を使用致しますが、まれに強い感染が起こることがあり、薬の変更や鼻の処置が必要になることがあります。
- 痛み、圧迫感等:手術後、鼻や頭の痛みが数日出ることがあります。痛み止めを処方し対応します。圧迫スポンジ挿入中は圧迫感や鼻づまりが辛いことがあります。
- 鼻中隔穿孔:手術により鼻中隔に穴が残ることがあります。穴があってもほとんどが鼻の機能に影響を与えませんが、大きな穴があいた場合など必要時は閉鎖術を後日に行うことがあります。
- 鞍鼻(あんび):鼻の支えとなる軟骨・骨をとりすぎてしまうと、鼻が落ち込んでしまうことがあります。通常は前1cm、上1cmは残す必要があります(前方や上方の矯正には限界があります)。
- 鼻中隔血腫・鼻中隔膿瘍:軟骨や骨を取り除いた後の空間に、血液や膿(うみ)が溜まってしまうことがあります。上述の感染や穿孔、鞍鼻のリスクとなるため、血腫貯留部を切開して、血液を出す必要があります。
- 鼻閉:術後しばらくは、粘膜の腫れにより鼻づまりが起こります。
手術後の治療
手術後は鼻内の経過を観察することが重要なため、定期的に外来通院して頂く必要があります。一般的には、手術後数日で再診、その1週間後に再診、その後2ヶ月間程度は、2週間に1回、その後は術後1年まで定期的に通院していただいております。手術後の経過により、必要な飲み薬や点鼻薬を使用していただきます。経過中粘膜の腫れが再発し、鼻づまりが起こった場合、追加治療(処置)が必要になることがあります。
手術以外の選択肢
手術以外の治療としては、内服(抗アレルギー薬、ステロイド)、点鼻薬(血管収縮薬、ステロイド)、ネブライザー(吸入)治療などがあります。基本的には、これらの保存的治療に抵抗性の鼻づまりが手術適当となります。